「環境のために私たちができること」
SID事業部 アドバイザーの井ノ瀬です。
メルマガより少し先の情報について「#Circular Economy(循環型経済)」をテーマに発信していきます。
「環境・社会報告書(E-VISION 2025)」はご覧いただけましたでしょうか?
組織再編を機に気持ちを新たに、「環境と資源を守る」ため、地域共創による付加価値の高い環境総合事業を推進していきます。企業としてはもちろんですが、私たち一人ひとりが、環境のために何が出来るのかを考え行動していきます。
6月中旬の記録的高温、人為的温暖化が要因
2025年6月26日、日本経済新聞に「極端気象アトリビューションセンター(WAC)は、6月中旬の記録的な高温は、地球温暖化による気温の上昇に、日本列島を勢力の強い太平洋高気圧が覆ったことなどが重なって発生したとの分析を発表した。人為的な温暖化がなければこうした高温は起こりえなかったと結論付けた。」と掲載されました。
「イベント・アトリビューション(Event Attribution)」※による分析結果とされています。
※特定の異常気象(猛暑、大雨、台風など)が人為的な地球温暖化によってどの程度影響を受けたかを科学的に評価する手法
人為的温暖化の主な原因
人為的な地球温暖化は、主に以下の3つが原因とされています。
①化石燃料の使用
石炭・石油・天然ガスなどを燃やすことで、大量の二酸化炭素(CO₂)が排出されます。
②森林伐採
森林はCO₂を吸収する役割がありますが、伐採によって吸収能力が低下し、温室効果ガスが大気中に残りやすくなります。
③農業・畜産
食料供給の根幹を担う一方で、飼育過程でメタンが、生産・輸送・加工の過程でCO₂が排出されます。
人為的温暖化は、私たち一人ひとりの行動が積み重なって生じる問題です。分かっていても日々の行動を変えることは難しく、つい「まぁ、いいか!」とごみの分別を疎かにしたり、食べ残したり、電気を消し忘れたりします。このブログを読まれている方々も、思い当たることがあるのではないでしょうか。
なぜ行動を変えることが難しいのか
環境に配慮した行動には、心理的要因が指摘されています。
環境問題に対する意識の高さと環境配慮的な行動を積極的にとることは一致しないとされています。
必ずしも「知識や意識=正しい行動」にはつながらないのです。
【環境問題に関する主な心理学的バイアス】
①心理的距離(Psychological Distance)
気候変動などの問題を「自分には関係ない」「遠い未来の話」と感じる傾向。この距離感が、行動意欲の低下や関心の希薄化につながる。
②確証バイアス(Confirmation Bias)
自分の信念に合う情報だけを選び、反対の情報を無視する傾向。
③社会的ジレンマ
環境問題への対応は、新たな労力やコストが必要になるため、個人の利益とは相容れないことが多い。
④経験の消失(Extinction of Experience)
自然との接触が減ることで、環境への関心や保全意識が低下する。都市化やデジタル化が進む現代で特に懸念される現象。
⑤社会規範バイアス
周囲の人が環境配慮行動をしていないと、自分も行動しなくなる。逆に、地域やコミュニティの連帯感が強いと行動が促進される。
裏を返せば、この心理的要因に働きかけることが出来れば行動を変えることができます。
注目したい「社会的有効性感覚」
日本人は、自然環境に対する意識よりも、自身の行動が社会全体の環境の維持に役立つという信念である「社会的有効性感覚」が環境保全活動に影響することが指摘されています。
集団における他者や地域との関係のあり方が、環境配慮行動を呼び起こすための重要な要因になると考えられています。
(参照:「環境配慮行動に影響を及ぼす「心理的諸要因」に関するレビュー」法理 樹里 氏 2024.7)
この「自分の行動や意見が社会や政治に影響を与えることができる」という感覚は、政治参加の促進や民主主義の健全性とも関わっています。
感覚を育てるには、課題解決型学習(PBL:Project Based Learning)が有効とされているので、環境保全活動とPBLを組み合わせるとより高い効果が期待できるでしょう。
企業として、一個人として、こうしたことを念頭に、環境保全活動の継続的な推進を図り、資源循環型社会形成の一翼を担ってまいります。

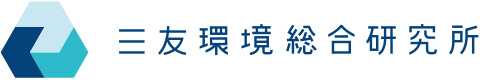

 パートナー
パートナー CONTACT
CONTACT
